
 仙台一高吹奏楽部には様々な係・役職があり、全員最低一つは係につくシステムだという。 全員にお話を伺いたいぐらいだが、まずは音楽監督の3人(実際は4人だが今回1名欠席)、そして金管セクションリーダーと副部長を兼任している橋本さんにも加わって頂いた。 ◆音楽監督 林郁美さん(2年生、オーボエ) 川田泰義さん(2年生、パーカッション) 大城榛音さん(1年生、ユーフォニアム) ◆金管セクションリーダーと副部長を兼任 橋本凌河さん(2年生、トロンボーン)  まず、仙台一高吹奏楽部での音楽監督とは具体的にどのようなことを行うのか伺った。 「音楽監督は練習日程を組み立てて、1日の基本的な練習計画を考えています。パート練習、個人練習の時間設定を考えるのも音楽監督です。この日はパート練習しよう、個人練習しよう、セクション練習しようって決めるのは、パートリーダーと音楽監督で話し合って決めることが多いです。 基礎合奏を仕切るのも基本的に音楽監督です。毎回、呼吸法、「コールユーブンゲン」をやっています。呼吸法はみんなで呼吸を揃えるのですが、他の学校のようにブレスを「シー」と吐くのではなく普通に「フー」で吐きます。基本的な呼吸を身に付けることを意識しています」(林) 合唱の教本を使いみんなで歌う練習をすることにはちょっと驚かされた。全員で正しい音程感を身に付けて、みんなで合わせて歌うことをやってから、楽器に移るようにしているのだという。 打楽器パートも一緒にやっているのだろうか? 「呼吸法のときは、スティックを使ってウォーミングアップしています。「コールユーブンゲン」の時は混ざっています」(川田) 吹奏楽部の基礎練習を支える音楽監督。 1年生の大城さんはなぜこの係につこうと思ったのか、きっかけについて伺った。 「中学のときからこういう係をやっていました。高校に入って先輩方が仕切っているので、かっこいいなあと憧れて。裏も表もできて一から物事を組み立てていくのが好きです」(大城) 中学ではトランペットを吹いていたが、高校ではトランペット希望者がとても多くユーフォニアムを選んだという大城さん。一年生もしっかりと落ち着いて係の仕事をしている様子がとても印象的な部だ。 音楽監督はセクション練習の内容も指示するのだろうか? 「セクションリーダーは別にいるんです。木管のセクションリーダーは私が兼任しています。もう一人、金管のセクションリーダーは副部長を兼任しています」(林) 音楽監督が4人いればアイディアも4通りあるだろうし、さらにはパートリーダー、セクションリーダーもいれば意見は様々。意見の交わし方や工夫していることはあるのだろうか? 「私たちは主張するのがすごくて、"絶対私はこれがいい!"、"いや、それは違う!"というのがよくあるんですけど、でもそれだからこそ、ぶつかってこそ一緒に上を目指せると思ってます。みんな音楽面で遠慮はしないです」(林) 意見を言い合った後は、どのように演奏に反映させているのかが気になるところだが・・・ 「基本的には出てきたパターンを何パターンかやってみて、それで大体は一つの方向にまとまっていきますね。まとまらない時は先生に相談します」(川田) 音楽監督は楽譜やスコアを読む機会が他の部員に比べて多いことと思う。楽譜には正解がなく、追求していくとどこまでも奥が深い。そことどう向き合っているのかについて最後に伺った。 「コンクールでは苦戦しました。"インテルメッツォ"やったんですけど、分からないことだらけでした」(林) 「譜読みのときは、自分の中のものしか出せないので、理屈ではなく自分が納得するまでとりあえずやってみます」(橋本) 仙台一高ではジャズの曲もよく演奏しており、ジャズを仕切るリーダーもいるのだという。ビッグバンド編成だが、オーボエやホルンの部員も演奏に参加できるよう工夫している。 音楽に関する向上心を持ち互いを高めようとしている姿が印象的だった。   次に登場頂くのは「学ビック(まなびっく)」のお2人。そもそも「学ビック(まなびっく)」とは?? ◆学ビック(まなびっく) 柏美宇さん(2年生、クラリネット) 狩野山亘輝さん(1年生、バストロンボーン)  「数学の小テストがあるんですけど、60点未満とっちゃうと追試なんです。 部活の時間を削って追試に出なきゃならなくなるので、それを未然に防ぐため追試にひっかかった人、夏休みサマースクール(補習)になっちゃった人は一覧表に○をつけることになっています」(柏) 誰一人欠けてほしくない、みんなで揃って演奏したいという思いから出来た係「学ビック(まなびっく)」。 自らも学業を怠らないように心がけつつ、仲間にも勉強するよう呼びかけるというのはなかなか難しい立場と思われる。 係の部員から、他の部員への呼びかけはどのように行っているのだろうか。 「小テストや追試の日程を自分で調べて、それまでに勉強しておいてください!と呼びかけを行います」(狩野山) 「今後、テスト前に行うワーク(宿題)を終わらせたかどうかチェックする欄も作ろうと思っています」(柏) まず自分たちがお手本になろうという二人。勉強と部活の両立をする上で、一高にとって欠かせないポストである「学ビック」。 いい音楽を作るためにも「学ビック(まなびっく)」にはこれからも頑張ってほしい。  ◆佐藤栞さん(1年生、フルート) 部員インタビュー、最後は、中学校から吹奏楽部に入っていた部員が圧倒的に多い中、唯一高校からフルートを始めたという、佐藤栞さんにお話を伺った。 ピアノをずっと習っていて音楽は元々好きだったとはいえ、今までやっていなかった吹奏楽を高校でやろうと思ったきっかけは何だったのだろう? 「吹奏楽部には中学のとき入りたかったけど、事情もあり親に反対されて運動部に入りました。 公立高校に受かったら入っていいよと言われて・・・受かったので入りました」(栞) 念願叶って仙台一高に合格。そして入った吹奏楽部。定番の教則本「バンドスタディ」を参考にしながら今も苦手なタンギングの上達に向け基礎練習に励む日々だ。初心者で入ってきたのは栞さんだけという環境、寂しさは無いのだろうか? 「初めの頃は、辞めたいとしか思ってなかったです。ちょっと病んだ時期があって(笑)。サックスから、高校に入ってフルートになった子がいるんですけど、一緒に練習しているときに何を思ったのか2人で号泣してしまったこともありました。劣等感はもちろん、みんなへの申し訳なさみたいなのが大きくて」(栞) 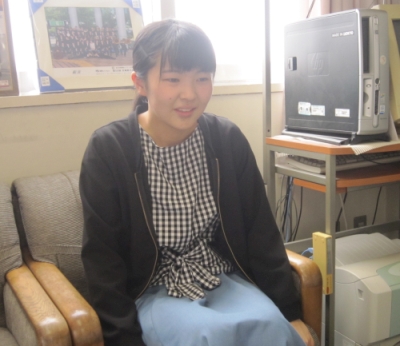 それでも辛さを乗り越えて今も部活を続けている栞さん。頑張ろうと思ったきっかけは何だったのだろう? 「同学年の子で、中学から楽器変わった子もいっぱいいて、みんな頑張って上手くなってるのを見て、自分にも出来るかなあと、同級生から刺激を受けました。パートの先輩も丁寧に教えてくれるので、最後までちゃんとやらないとなあっていう使命感、そして単純に楽しくなってきたというのもあります」(栞) 仲間の存在の大きさに気付き、楽器の上達とはまた違った大事なものを手に入れた栞さん。 いま吹奏楽部に入ろうか迷っている読者、初心者で頑張っている読者に栞さんからのメッセージをお願いした。 「最初は入るのに勇気がいると思います。あきらめないでやってみて、やってみるのが大事だと思う。自分一人で部活とか楽器を吹くのではなく、支えられてる部分も大きいので、そういう仲間意識とか"みんなでやってる"って感じがあるのが、すごくいいと思います」(栞) ステージで一段と自信を持って演奏している栞さんにまたぜひ再会したい。  番外編:一高生に聞いてみました!<将来の夢> 物理の研究者、生物の研究者、国家公務員(省庁勤務)、医工学を学びたい、国際関係の仕事に就きたいなど夢は様々。皆さん堅実な夢が多いですね。 音楽関係では、音響関係の仕事を考えていたり、教員になって吹奏楽部の顧問になりたい!という方もいました。  ◆3ページ目に続く⇒ |
